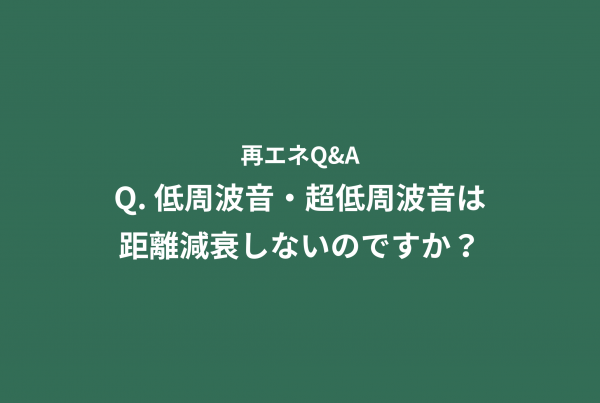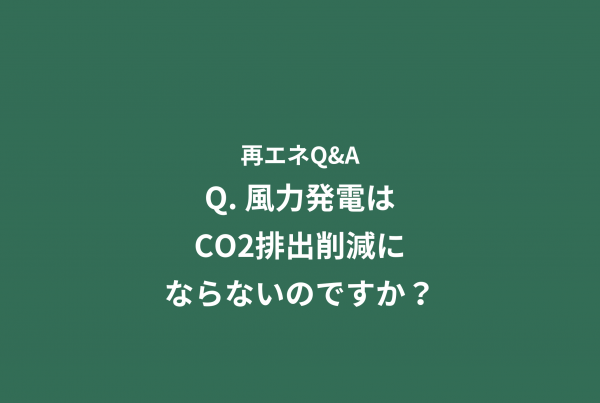名古屋大学大学院環境学研究科研究員 平春来里
A. 研究レビューから、風力発電機から生じる低周波音や超低周波音のレベルが生理学的な影響をもたらすと裏付ける研究はありません。
聴覚のしきい値を下回る低周波音や超低周波音が内耳や蝸牛に直接悪影響をもたらす可能性を指摘する研究もありますが、それを主張する研究では十分な知覚のメカニズムが説明されていません。また、てんかんや心血管系の疾患リスクを主張する研究は、風力発電よりも高い振動暴露をもたらす航空機等による騒音の健康影響の知見に基づいています。
このコラムでは間接的な人体への影響として睡眠障害がもたらされる研究に関しても知見を整理しました。日本での調査からは、風力発電機から住宅の距離を離すと睡眠障害が減少することが示唆されています。ただ低周波音に関する症状については交絡因子が多いため、音の物理特性とは別の風力発電の導入に対する個人的態度や経済的恩恵の有無といった社会的・心理的な要因の影響を考慮する必要があると言われています。
解説
低周波音・超低周波音1低周波音は概ね1Hz〜100Hzの音のことをさし、中でも人間の耳では聞こえにくい20Hz以下の音は超低周波音と呼ばれています[10] 。環境省では「低周波音」を「おおむね100Hz以下の音」として定義してきましたが、国ごとにその周波数範囲が異なるため、その用語の使い方には注意が必要です[8]。環境影響評価法においては「低周波音」という用語は用いないこととされています[8]。による健康影響に関する知見のうち、まずは生理学的な影響について整理します。2014年に耳の専門家であるSaltとLichtenbanが、風力発電から発生する低周波音や超低周波音は、聴覚しきい値を大きく下回るレベルであっても、長期間さらされることによって内耳や蝸牛が反応し、結果としてめまいや耳鳴りを及ぼす可能性があると指摘しました[1]。Saltらは低周波音が聴覚で知覚されなくとも生理学的影響をもたらすことを主張します。しかし、この研究では20Hz以下の超低周波音の知覚のメカニズムが不明であり、暴露に対する人体の反応の関係も明らかではありませんでした。そこで、あらゆる国で超低周波音の知覚とヒトへの影響に関する研究プロジェクトが実施されるようになりました[2]。そのひとつが、欧州地域を対象に実施されたEARSプロジェクトです。このプロジェクトは超低周波音および超低周波に関連する健康被害から人々を保護することを目的に、6年間をかけて実施されました[2] [3]。EARSプロジェクトについて詳細な報告をしている横山・小林・山本[3]によると、EARSプロジェクトでは音源発生装置を用いた聴覚閾値実験が行われ、聴覚閾値、うるささ、アノイアンスに関する主観評価と、脳磁図(MEG)や機能的磁気共鳴画像(fMRI)を利用したヒトの脳反応が調査されました。Saltらの研究では音響刺激が直接脳反応をもたらす可能性が指摘されましたが、EARSプロジェクトの実験から、音圧レベルによる音響効果は聴覚による知覚がなければ脳反応が生じないという結果が得られました[3]。この研究成果は欧州を中心に支持を得ており、IEC規格やドイツの騒音規制法等では、聴覚閾値を基準として超低周波音の健康影響を検討する方針がとられています[3]。
低周波音や超低周波音が耳や脳以外に影響をもたらすかについて検討した研究もあります。超低周波音による自律神経系に対する影響を実験2被験者は実際に風力発電所の周辺に居住する人27名(データ使用は26名)で、主観的に低周波音と関連づけた症状を持つ人と、症状を持たない人を2つのグループに分けて実験を行った。そこで低周波音を含む実際のレベル(風力発電所から約200m離れた場所、約1.5km離れた家屋の庭と家屋内)で再現された風力発電機の録音を、対照実験室の刺激として使用した[4]。録音された風力発電所は定格出力が3,000kW程度の17基の風力発電機からなる[4]。参加者のグループ間で感度を比較したところ、差は見られなかった[4]。によって調べたフィンランドのMajialaら[4]によると、超低周波への曝露に反応して、心拍数、心拍変動、また皮膚コンダクタンス3皮膚コンダクタンス(Skin conductance)とは、皮膚表面の電気の流れやすさを表し、これは覚醒水準として用いられている[11] 。に有意な変化は見られなかったといいます。実験では、低周波音を知覚できるのかどうかも調査され、可聴音の存在下で低周波音に対する感度がきわめて低いという結果も得られました[4]。したがって、低周波音による主観的な症状は、音の物理特性とは別の要因によって誘発される可能性が高いと結論づけられています[4]。
風力発電から発生する低周波音や超低周波音による健康影響が懸念される際は、より音圧レベルの大きい航空機から発生する低周波音や超低周波音による健康影響に関する知見に依拠している場合もあります。Alves-PereiraとCastelo Brancoは風力発電機から発生する低周波音や超低周波音が、てんかんのリスク増加や血管系への影響といった「振動音響病」(Vibroacoustic disease : VAD)を引き起こす可能性や、蝸牛の繊毛が融合することで不快感を生じる可能性があると主張しています[5]。しかし彼女らの指摘は、おもに航空機整備に関わる整備士などの、高い振動暴露状況にある場所で作業に従事しなければならない人々の健康影響を主張の根拠としています。また蝸牛の反応に関する知見は動物実験による知見にとどまっており、人体でも同様の症状が生じるのかは明らかではありません。この主張を、低周波音と超低周波音の振動暴露が低レベルである風力発電機の議論に接続させるには注意が必要です。音響工学の専門家らは、Alves-PereiraとCastelo Branco[5]の議論は仮説の段階にとどまっているため、風力発電機から発生する低周波音と超低周波音に関連する問題の証拠としては知見が不足していると指摘しています[6]。一部の研究では風力発電機から発生する超低周波音が、アドレナリンの分泌を増加させ、敏感な人にストレス作用を引き起こす可能性があることが示唆されていますが、この見解は他の研究では広く支持されているものではありません[7]。
続いて、間接的な影響について整理します。 風車タービンからの可聴音と超低周波音が睡眠に及ぼす影響については日本においても調査が行われています。石竹[8]は鹿児島県出水群長島町を対象とした騒音の計測調査とアンケート調査を行ないました。騒音の計測調査では町内の合計72箇所で24時間連続して行われました。アンケート調査は町内の自治会に加入している全世帯を対象とし、2,593通(回収率28.3%)が得られました。その調査によって得られた騒音のデータと睡眠の不調との関係を調べたところ、風車から5km未満までは距離と睡眠障害の間に統計的に有意な関連があると認められています[8]。このように、十分に距離を離しても睡眠の不調が必ず減少するわけではないことがわかっています。加えて、同調査からは、この地域の住民は風力発電よりも自動車の騒音に対してわずらわしさを感じていることも明らかになっています。回答者のうち25%が自動車からの騒音が最もわずらわしいと感じ、風力発電がもっともわずらわしいと感じる人は8%という結果でした[8]。超低周波音については、他の騒音と比べてもあまり相違がなく、睡眠への影響については確認されていません[8]。ただ交絡因子である煩わしさ(アノイアンス)に影響する可能性は否定するものではないとされています[8]。
アメリカ風力発電協会とカナダ風力発電協会[9]によるレポートでも可聴音、低周波音、超低周波音による人体への直接的な影響は確認できないと言われていますが、近年の研究成果を踏まえても、可聴音である風車騒音と、風力発電機から生じる低周波音や超低周波音のレベルでは生理学的な人体影響を直接及ぼすことを裏付けるような研究はありませんでした。風車騒音は他の騒音と比較すると、同程度の騒音レベルであっても迷惑と感じるという特性があり、睡眠に及ぼす影響については注意が必要です。日本でも風力発電機からの可聴音と超低周波音が睡眠に及ぼす影響について実際の風力発電サイトでの調査が行われています[8]。その調査では距離を離すと睡眠障害が減少することが示唆されています。ただ低周波音に関する症状については交絡因子が多いため、音の物理特性とは別の、風力発電の導入に対する個人的態度や経済的恩恵の有無といった社会的・心理的な要因の影響を考慮する必要があると言われています。
参考文献
[1] Salt, Alen N. and Jeffery T. Lichtenban, 2014, How does wind turbine noise affect people?, Acoustics Today, 10(1): 20–28.
[2] European Metrology Research Programme(EMRP), 2016, Metrology for a universal ear simulator and the perception of non-audible sound (EARS project) Final Publishable Report,(2025年6月27日取得, https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/metrology-for-modern-hearing-assessment-and-protecting-public-health-from-emerging-noise-sources)
[3] 横山栄・小林知尋・山本貢平, 2021, 「欧州における超低周波音知覚に関する研究動向」『日本音響学会誌』77(12): 772-774.
[4] Maijala , Panu P., Ilmari Kurki, Lari Vainio, Satu Pakarinen, Crista Kuuramo, Kristian Lukander, Jussi Virkkala, Kaisa Tiippana, Emma A. Stickler, Markku Sainio, 2021, Annoyance, perception, and physiological effects of windturbine infrasound, Journal of the Acoustical Society of America, 149(4): 2238–2248.
[5] Alves-Pereiraa, Mariana, and, Nuno A.A. Castelo Brancob, 2007, Vibroacoustic disease- Biological effects of infrasound and low-frequency noise explained by mechanotransduction cellular signalling, Progress in Biophysics and Molecular Biology, 93: 256-279.
[6] Bolin, Karl, Gösta Bluhm, Gabriella Eriksson and Mats Nilsson, 2011, Infrasound and Low Frequency Noise from Wind Turbines- Exposure and Health Effects, Environmental Research Letters, 6.
[7] Enbom, Håkan, Inga Malcus Enbom, 2013, Infrasound from wind turbines-an overlooked health hazard, Läkartidningen, 110: 1388.
[8] 石竹達也, 2018, 「風力発電施設による超低周波音・騒音の健康影響」『日本衛生学雑誌』73(3): 298-304.
[9] American Wind Energy Association and Canadian Wind Energy Association, 2009, Wind Turbine Sound and Health Effect: An Expert Panel Review. (2025年6月27日取得, https://www.novoco.com/public-media/documents/awea_soundwhitepaper_121109_0.pdf)
[10] 環境省, 2007, 『よくわかる低周波音』(2025年6月9日取得, https://www.env.go.jp/air/teishuuhaon1zenntai.pdf)
[11] 長野祐一郎, 永田悠人, 宮西祐香子, 長濱澄, 森田裕介, 2019, 「IoT皮膚コンダクタンス測定器を用いた授業評価」『生理心理学と精神生理学』37(1): 17-27.