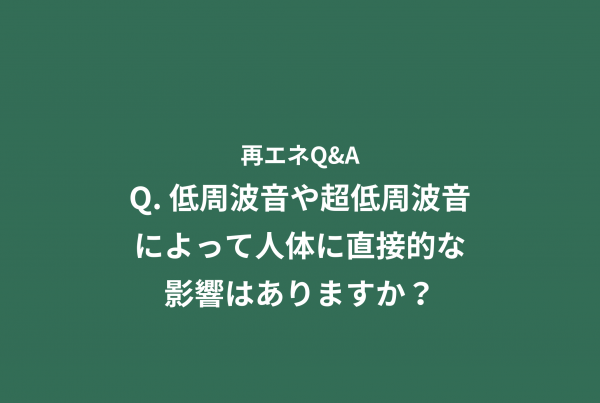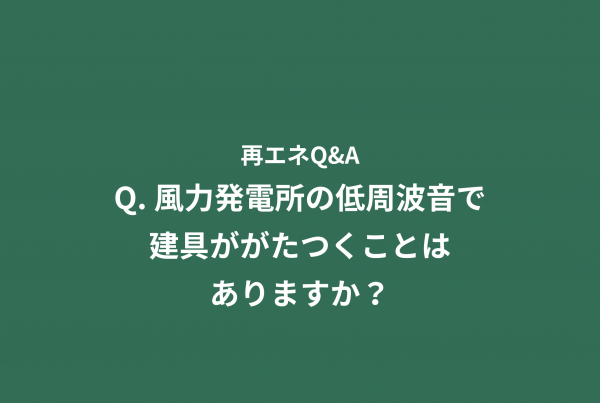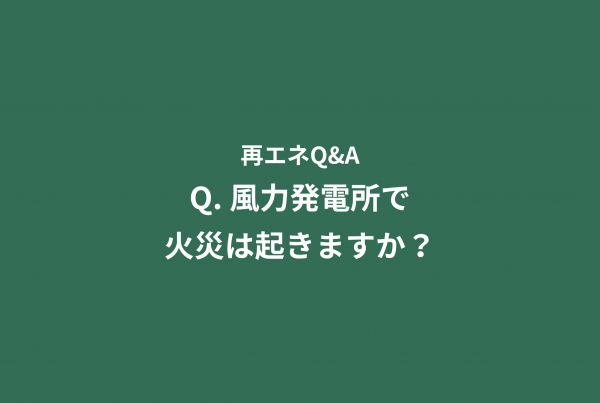名古屋大学大学院環境学研究科特任准教授 本巣芽美
A. 脱炭素に向けて、火力発電を再エネや原子力など非化石の発電に置き換える必要があります。電力需給バランスを維持するために太陽光や風力が出力抑制される場合がありますが、これらの再エネ発電所を制御せずに稼働させたとしても、火力発電に置き換わるほどの発電量は見込めません。
仮に、停止中の原子力発電所を稼働させたとしても、火力発電による発電量には匹敵しません。したがって、電気や発電所が余っていても、新たな再エネ開発は必要と考えられます。
また、電力は予備率の確保が必要であるため、基本的に発電所は余っていることも重要です。さらに、セクターカップリングを行えば、余剰電力を無駄なく効率的に利用することもできます。
解説
日本の発電電力量は2023年度現在、1兆106億kWhです [1]。このうち火力発電(バイオマスを除く)が占める割合は72.8%であり [1]、発電電力量は約7,357億kWhとなっています。脱炭素に向けて、この発電量を再エネに置き換えていく必要があります。
まず、電気や発電所が実際に余っているかを検証します。電力は発電量と消費量を一致させる同時同量の原則があるため、発電量が消費量を上回る場合は、優先給電ルールに基づいて火力発電の出力制御や揚水、蓄電池の活用、地域間連系線を使った他エリアへの送電が行われます [2]。
それでも発電量が上回る場合には、バイオマス発電、太陽光発電、風力発電の順に出力制御されます [2]。
このため、制御される発電量や発電所を「余っている電気」「余っている発電所」と捉えるのであれば、電気は余っていると言えます。また、老朽化や発電効率の低さから休止している火力発電所や、東日本大震災後に停止中の原子力発電所も多く、発電所は余っていると言えます。
では、これらの余っている電気や発電所を稼働させれば、新たな再エネは不要なのでしょうか。
経済産業省が2024年度に発表した各エリアの再エネ出力制御見通しの合計は約24億kWhであり、これを出力抑制せずに発電したとしても、前述の火力発電による発電量には及びません。
表1. 各エリアの再エネ出力制御率(%)と制御電力量(kWh)見通し
| 北海道 | 東北 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 2024年度 | 0.2%
[0.1億kWh] |
2.5%
[4.0億kWh] |
0.6%
[1.0億kWh] |
1.1%
[0.2億kWh] |
0.7%
[0.8億kWh] |
5.8%
[5.7億kWh] |
4.5%
[2.4億kWh] |
6.1%
[10億kWh] |
0.2%
[87万kWh] |
| 2023年度 | 0.01%
[50万kWh] |
0.93%
[1.47億kWh] |
0.26%
[0.41億kWh] |
0.55%
[0.10億kWh] |
0.20%
[0.18億kWh] |
3.8%
[3.50億kWh] |
3.1%
[1.63億kWh] |
6.7%
[10.3億kWh] |
0.14%
[74.3万kWh] |
データ出典:資源エネルギー庁資料 [6] を元に筆者作成
また、休止中の発電所を再開する点については、停止中の原子力発電所をすべて稼働させたとしても、2011年以前の状態に戻るだけです。2010年度の原子力発電の発電電力量は2,882億kWh [3] であったため、やはり火力発電の代替にはなりません。
また、発電所は基本的に「余っている」状態が必要です。これは、電力の予備率を確保するためです。
予備率とは、「電力需要に対して供給余力がどの程度あるかを示すもの」であり [4]、発電設備の点検やトラブル時にも供給を維持するため、最低でも3%の予備率が必要とされています [4]。
以上のことから、再エネの出力抑制を行わずに発電可能な量を供給したり、休止中の発電所があっても、新たな再エネ開発は必要だと言えます。
近年では、猛暑や寒波により電力が逼迫するケースもあります。その不足分を補うために、二酸化炭素排出を全く考慮しないのであれば、老朽化した火力発電所の活用も考えられます。しかし、脱炭素を進めるためには化石燃料から再エネへのエネルギー転換が必要であり、それがふさわしい方法ではありません。
また、余剰電力の無駄を減らす方法として、「セクターカップリング」が注目されています。
電力は同時同量の原則があるため、火力発電や再エネの出力制御によって調整されますが、セクターカップリングは、この調整力を電力部門だけで対応するのではなく、熱や交通、産業といった他の部門(セクター)と統合させることで、余剰電力を無駄なく効率的に利用する方法です。
例えば、ドイツでは風力発電の余剰電力を熱に変換し、温水を作ることで地域暖房システムを構築しました [5]。このような方法により、他の部門のエネルギー需要にも対応できるため、エネルギー全体を見据えた発想への転換が、電力の無駄を減らすためには重要です。
参考文献
[1] 経済産業省, 令和4年度(2022年度)エネルギー受給実績(確報)(令和6年4月12日公表), (2024年7月31日 取得, https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/gaiyou2022fykaku.pdf)
[2] エネ庁,(2024年8月2日取得, https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_syuturyokuseigyo.html)
[3] 経済産業省資源エネルギー庁, エネルギー白書2023, 第2部エネルギー動向,(2024年9月26日取得, https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2023/pdf/2_1.pdf)
[4] 経済産業省資源エネルギー庁, 電力需給状況, 2023年2月3日,(2024年9月2日取得, https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/jokyo.html)
[5] 西村健佑, 京都大学大学院経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座「No.297 ドイツのエネルギーシステムの未来を占う実証プロジェクト群『SINTEG』第4回 フレキシューマーの登場とセクターカップリングの可能性」, 2022年2月17日, (2024年9月2日取得, https://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/stage2/contents/column0297.html)
[6] 経済産業省資源エネルギー庁, 再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について, 2024年3月11日, (2024年8月2日取得, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_01_00.pdf)