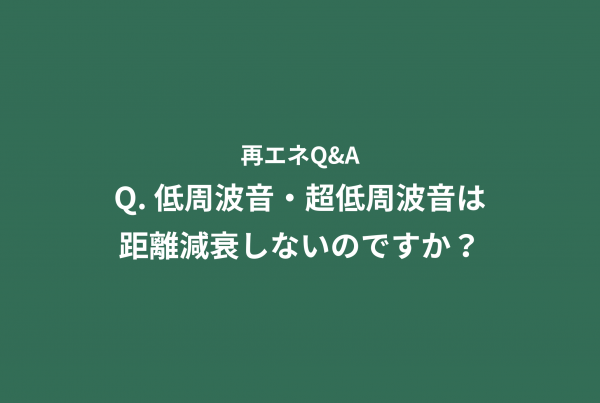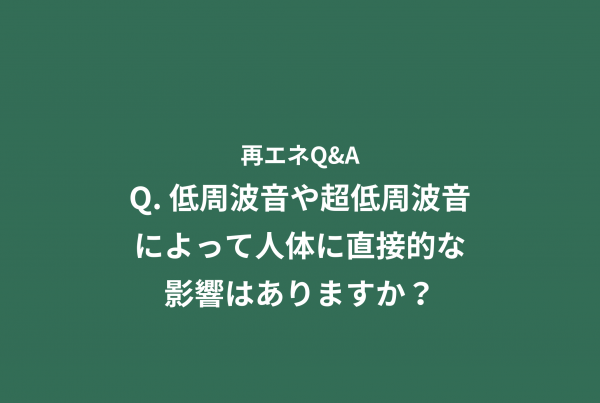名古屋大学大学院環境学研究科特任准教授 本巣芽美
A. 風力発電所はバックアップ電源として火力発電所が必要であるため、風力発電所が増加すると火力発電所も増加し、結果、二酸化炭素の排出量が増加するという主張があります。しかし、風力発電だけで電力需給を予測し不足分を火力発電で補うのではありません。また、風力発電を含む再エネと原子力発電の増加により、火力発電の割合は減少しています。風力発電の増加は二酸化炭素の排出削減にむしろ貢献していると言えます。
解説
風力発電所の建設によって二酸化炭素の排出量が増加し、結果として地球温暖化を助長しているという主張があります。その理由には、風力発電所のバックアップ電源として火力発電所が必要であるため、新たな火力発電所の建設により火力発電所が増加し、また、常に火力発電所を待機状態としなければいけないため、無駄なエネルギーを消費し二酸化炭素の排出量が増加するという考えがあるためです。しかし、実際には、風力発電が原因で火力発電が増えているという事実はありません。
まず、バックアップ電源1変動する発電量への対応として、国際的にはバックアップという考え方ではなく、柔軟性という考え方が主流です。としての火力発電は、風力発電だけの電力の増減で、電力需給を予測し出力を制御するのではありません。原子力発電や地熱発電といった短時間で出力制御を行わないベースロード電源(長期固定電源)、風力発電、太陽光発電といった変動性の電源、火力発電などの出力制御が容易な柔軟性のある電源から、電力需要に合わせて電力を供給します。そして、需給バランスを維持するために、優先給電ルールにしたがい供給量を調整する仕組みとなっており、その調整には、火力発電の他、地域間連系線の活用、揚水、蓄電池、水力発電など複数の方法があります(詳細は、コラム「電気が余っているのに、なぜ再エネが必要なのか?」をご参照ください)。
実際のところ、電源構成比と事業用発電のCO2総排出量を比較すると、再エネの増加とCO2の増加は比例していません(図1)。また、2023年度の電源構成比では、風力発電の割合は1.1%、火力発電の割合は68.6%ですが、第7次エネルギー計画の2040年の目標では、風力発電は4〜8%、火力発電は30〜40%です[1]。すなわち、風力発電を含む再エネの増加は火力発電の増加やCO2排出量の増加には結び付きません。エネルギー種別ごとの発電量の推移を参照しても、再エネの発電量が増加すると火力の発電量が絞られていることがわかります(図2)。
最後に待機状態についてですが、電力需給バランスの維持のために火力発電からの電力を制御している間、火力発電所では蒸気を捨てながら待機しているため無駄なエネルギーを消費しているという主張がありますが、この解釈には注意が必要です。電力の安定供給のためには、予想される最大電力需要に対して最低でも3%の供給可能な電力量を確保することが求められています。これを「予備率」と言います。この予備率を確保するために「待機予備力(停止状態)[2]」「運転予備力(10分程度で起動)[3]」「瞬時予備力(10秒程度で起動)[4]」の3種類の予備力があります。変動性の再エネに限らず、猛暑や寒波による電力需要の急増や災害による電源の脱落などにより、急な電力供給が必要となる場合があるため予備力を確保することは重要です。その際、全ての予備力の発電所がフル稼働し空焚きするのではなく、例えば、東北電力であれば当日の最大電力想定値に対し5〜8%程度の運転予備力を確保し、電力需要予測の3%程度の瞬時予備力を確保することとなっています[5]。すなわち、電力として使用されない発電所はありますが、予備力によって二酸化炭素の排出量が増加しているわけではありません。また、予備力は電気を安定して供給するための電力システム全体に対して余力を確保するものであり、エネルギー構成比とは関係がありません。
図1 電源構成比と事業用発電のCO2排出量の推移
(国立環境研究所[6]及び資源エネルギー庁[7]のデータより筆者作成)
図2 2023年4月1日の発電量推移[8]
参考文献
[1] 経産省, 2025, エネルギー基本計画の概要, (2025年9月2日取得, https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_02.pdf)
[2] 電気専門用語集, 待機予備力, (2025年9月2日取得, https://jec-iee.org/jec_ev/New_Yougo_Teigi.php?yougo_no=2.09.1&yougoshuu_no=5)
[3] 電気専門用語集, 運転予備力, (2025年9月2日取得, https://jec-iee.org/jec_ev/New_Yougo_Teigi.php?yougo_no=2.09.2&yougoshuu_no=5)
[4] 電気専門用語集, 瞬時予備力, (2025年9月2日取得, https://jec-iee.org/jec_ev/New_Yougo_Teigi.php?yougo_no=2.09.3&yougoshuu_no=5)
[5] OCCTO, 2015, 第3回調整力等に関する委員会 資料2 参考「短期断面における調整力確保の考え方〜一般電気事業者からの提出資料〜」, (2025年9月2日取得, https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2015/files/chousei_03_02_sankou.pdf)
[6] 国立環境研究所, 2025, 日本の温室効果ガス排出量データ, (2025年9月2日取得, https://www.nies.go.jp/gio/archive/ghgdata/index.html)
[7] 資源エネルギー庁, 2025, 【第14-1-6】発電電力量の推移, (2025年9月2日取得, https://www.enecho.meti.go.jp/about/energytrends/202506/html/s-1-4.html)
[8] ISEP, 発電量の推移, (2025年9月2日取得, https://isep-energychart.com/graphics/electricityproduction/?region=all&period_year=2016&period_month=4&period_day=1&period_length=1%20week&display_format=residual_demand)